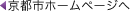令和5年度 上京民生児童委員会 生活支援・防災専門部会研修会について
ページ番号317264
2023年9月14日
生活支援・防災専門部会研修会の実施
上京区役所と上京民生児童委員会とが連携して、上京民生児童委員会 生活支援・防災専門部会研修会を実施しました。専門部会は、生活支援・防災、高齢者福祉、障害者福祉及び児童母子福祉の4部会あり、今回は「『避難行動要支援者名簿』の活用について ~待賢学区での取組事例~」と題して講演を行いました。
参加者からは「避難行動要支援者名簿の読み方について、具体的な例を入れての説明が大変勉強になった」「今まで考えてこれなかった内容を聞けてよかった」「要支援者について、日常の活動の中でしっかりと把握することが大切であると感じた」「災害時の民生委員活動には限界があると感じている。今日の研修を自主防災とも共有したい」「家族状況、認知症、内部障害など日ごろからのお付き合いで得た情報が災害時に活きる」などの声が聞かれました。
【対 象】
生活支援・防災専門部会所属の民生委員・児童委員及び主任児童委員 55人


研修会
「避難行動要支援者名簿の活用について」 ~待賢学区での取組事例~
(1)日時
令和5年9月13日 水曜日 10:00~
(2)場所
上京区役所 4階大会議室
(3)次第
開会挨拶 生活支援・防災専門部会 部会長 原 吉則
報告講演 待賢学区民生児童委員協議会 会長 原 吉則
閉会挨拶 生活支援・防災専門部会 副部会長 深尾 康史
(4) 概要
〇災害時の民生委員が為すべき事を考える。
〇避難行動要支援者名簿の読み方を学ぶ。
〇名簿を目的に合わせて再編成する。
1 京都市の避難行動要支援者名簿
2 被提供団体に期待されること
事前整理の重要性(要配慮者の確定、避難所での要配慮者の処遇)
3 要配慮者の再編成
自立行動(移動)ができるか、自立生活ができるか、電源を必要とするか、特に配慮を必要とするか
→名簿からの情報、認知症など日常活動からの情報
4 カテゴリー分類
実際の分類解説(人工呼吸器、認知症、内部障害(ペースメーカー、透析、在宅酸素等)、独居等)
要介護度の実像、障害支援区分の実像、障害者手帳・療育手帳の種類・等級の実像等の解説
5 待賢学区での再編成結果
6 避難行動要支援者名簿に関する問題提起
(参考)
■ 民生委員・児童委員について
厚生労働大臣から委嘱される非常勤の地方公務員であり、学区内の各々の担当エリアにおいて、援助を必要とする住民の生活に関する相談に応じたり、助言等の援助を行うことを主な職務とし、福祉行政の協力者として重要な役割を担うとともに、地域の諸団体とも連携して様々な福祉活動を展開しています。また、民生委員に委嘱された方は、児童福祉法の規定により、児童委員を兼ねることとされています。
■ 主任児童委員について
主任児童委員は、学区全体において児童福祉に関する問題を専門的に担当する児童委員で、児童福祉関係機関や児童委員との連絡調整を密にし、民生委員・児童委員の活動に対する援助、協力を行っています。
■ 人数等
民生委員・児童委員 159人(上京区)
主任児童委員 36人(上京区)
問合せ
上京区役所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課地域支援担当(2階㉖番窓口)
電話:075-441-2871 FAX:075-441-0180
お問い合わせ先
上京区役所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課地域支援担当(2階㉖番窓口)
電話:075-441-2871 FAX:075-441-0180