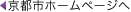「伏見区民史跡・名所めぐり」スポット一覧
ページ番号336748
2025年1月31日
現在、このページにてスポットを掲載しています。
※施設には入場料が必要な場合があります。
※施設の開場日や開場時間を予めご確認ください。
紹介スポット
| 順不同(五十音順) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 会津藩駐屯地跡の石碑 | 33 | 竹田火の見やぐら |
| 2 | 魚市場遺跡 魚魂碑 | 34 | 田中神社 馬の神様 |
| 3 | 延座参座 (えんざさんざ) | 35 | 谷口清兵衛金物店跡 |
| 4 | 大石天狗堂 | 36 | 電気鉄道事業発祥の地碑 |
| 5 | おせき餅 | 37 | 鳥羽伏見戦跡碑 |
| 6 | カワライ薬局 | 38 | 鳥羽伏見戦の弾痕跡 |
| 7 | 観月橋の親柱 | 39 | 羽束師坐高御産日神社 久我畷・羽束師川記念碑 |
| 8 | 寒天発祥の碑 | 40 | 羽束師坐高御産日神社 本殿 |
| 9 | 黄桜カッパカントリー | 41 | 東山酒造有限会社 酒蔵外観 |
| 10 | 京極屋 | 42 | 平戸樋門 |
| 11 | 京橋 | 43 | 伏見銀座跡 |
| 12 | 京・伏見大手筋カラクリ時計 | 44 | 伏見駿河屋本店 |
| 13 | 京都伏見珈琲 権十郎café | 45 | 伏見長州藩邸跡の石碑 |
| 14 | 金札宮 クロガネモチの木 | 46 | 伏見奉行所跡 |
| 15 | キンシ正宗 売店前正面 | 47 | 伏見桃山城 模擬天守 |
| 16 | 吟醸酒房 油長 | 48 | 伏見夢百衆 |
| 17 | 草津みなと残念石 | 49 | 松田桃香園 |
| 18 | 玄忠寺 伏見義民小林勘次碑 | 50 | 三栖閘門 |
| 19 | 戀塚寺(こいづかでら)袈裟御前戀塚 | 51 | 水ノ雅 KYOTO FUSHIMI |
| 20 | 久我大臣の墓 | 52 | 明壽院 伏見庚申堂 くくり猿 |
| 21 | 御香宮神社表門 | 53 | 向島中央公園 |
| 22 | 御大典記念埋立事業竣工碑 | 54 | 澱川橋梁 |
| 23 | ササキパン本店 | 55 | 淀城跡 |
| 24 | 薩摩島津伏見屋敷跡の石碑 | 56 | 與杼神社 銀杏と拝殿 |
| 25 | 橦木町(しゅもくちょう)廓之碑 | 57 | 淀水路の河津桜 |
| 26 | 城南宮 神苑 源氏物語 花の庭 | 58 | 淀の水車モニュメント |
| 27 | 勝念寺 かましきさん | 59 | 龍馬とお龍、愛の旅路像 |
| 28 | 勝念寺 天明義民柴屋伊兵衛墓所の碑 | 60 | 竜馬通り商店街 竜馬アート |
| 29 | 新地湯 | 61 | 長建寺 竜宮門 |
| 30 | 角倉了以水利紀功碑 | 62 | 安楽寿院 地図付き解説板 |
| 31 | 太閤堤址駒札 | 63 | 月の桂 株式会社増田德兵衞商店 |
| 32 | 大黒寺 金運清水 | 64 | 八千代大明神(平戸町) |
| 65 | 淀本町商店街 | ||
| 66 | 伏見区民文化祭・区民茶会 |
紹介スポット詳細
1.会津藩駐屯地跡の石碑

・京都市伏見区大坂町(東本願寺伏見別院前)
慶応3年(1867)の大政奉還以降に、会津藩は東本願寺伏見別院(伏見御堂)を拠点とした。
特に慶応3年暮から4年の年始にかけて、駐屯する兵力を増強し、
御香宮の新政府軍との軍事的緊張が頂点に達し、鳥羽・伏見の戦いの伏見口の戦いへと発展する。
2.魚市場遺跡 魚魂碑

・京都市伏見区横大路草津町(羽束師橋東詰南)
江戸幕府が設置を命じた公設の魚市場跡。
この地は、草津湊という古くからの水運・陸運の中継地で、桃山時代から江戸時代には魚市場があり、魚市場遺構の石碑が立てられている。3.延座参座 (えんざさんざ)

・京都市伏見区竹田桶ノ井町
道切り。丈六会が管理している。
勧請縄(かんじょうなわ)は、村境(地域・地区の域内・外のさかい)に、呪物を付した注連縄を張る習慣である。
名は廃社になった山王権現大宮社の座組織からといわれる。
4.大石天狗堂

・京都市伏見区両替町2丁目350―1
寛政12年(1800年)創業のかるたの老舗。
小倉百人一首に代表されるかるたをはじめ、囲碁・将棋などを通じて、日本の伝統美・日本の心・京の雅と遊びを現代に伝えている。
5.おせき餅

・京都市伏見区中島御所ノ内町16
永禄年間に創業した、創業400年以上にもなる老舗。
鳥羽街道にあった店舗は昭和7年(1932)京阪国道の開通により、伏見区国道1号沿いに移転。激動の時代を経て、営業を続けている。
6.カワライ薬局

・京都市伏見区新町4丁目
明治25年(1892)創業。
主に各種漢方薬、薬草、安心実績のある健康食品を取り扱っており、特に漢方専門メーカーのものを多く揃えている。
その中でも100年以上の歴史がある日本のオリジナル商品、大峯山の陀羅尼助丸、京都亀田の小児六神丸、阪本のまむし軟膏、奥田家下呂膏などが好評である。
7.観月橋の親柱

・京都市伏見区表町578 京都市建設局伏見土木事務所
江戸時代、豊後橋と呼ばれた観月橋は、明治6年(1873)、鉄橋にかけ替えられる。
京都市伏見土木みどり事務所敷地内で保存されている親柱はこの時のもの。
なお、現在の橋は昭和11年(1936)に明治の鉄橋からかけ替えられる。
8.寒天発祥の碑

・京都市伏見区御駕篭町97
寒天は17世紀後半に伏見で製法が考案される。
考案されたきっかけは参勤交代で伏見に滞在した薩摩藩主に給仕したところてんを寒ざらしにしたこととも伝わる。
江戸中期には御駕籠町に寒天仲間が組織された。
また、寒天を用いた練羊羹は大正時代まで伏見の名物として、その名を轟かせていた。
9.黄桜カッパカントリー

・京都市伏見区塩屋町228
酒造メーカー黄桜がオープンした地ビールと日本酒のテーマパーク。
レストランと黄桜記念館が併設されている。
10.京極屋

・京都市伏見区東大手町769
約100年以上にわたり地元の方々に愛されてきた「京極屋」。
伏見はもとより、日本各地の「日本酒」と「京つけもの」が自慢の品である。
レトロな看板が目を曳く店構えである。
11.京橋

・京都市伏見区京橋町
かつて大坂との間で淀川を往来した三十石船などが頻繁に接岸し、
昼夜の別なく、西国や京都、江戸に向かう旅人で溢れた東海道五十七次54番目の宿駅の中心。
橋の北側には寺田屋など数十軒の船宿も立ち並んでいた。
12.京・伏見大手筋カラクリ時計

・京都市伏見区銀座町362
「おやかまっさん」と呼ばれる、からくり時計は、毎時00分に音楽とともに扉が開き、 安土桃山時代の千利休が出てお茶を頂き、その後、幕末の坂本龍馬やお酒を造る杜氏など伏見ゆかりキャラクターが勢揃いし、商店街だけでなく伏見の名所となっている。
現在は調整中。
13.京都伏見珈琲 権十郎café
・京都市伏見区横大路草津町25−1
国の有形文化財である築150年の「藤田権十郎邸」をリノベーションした店内は、歴史を感じることができる趣のある空間である。
土間や広々とした座敷、光と影のバランスが絶妙の中庭など、現代の建物にはない風情が漂っている。
14.金札宮 クロガネモチの木

・京都市伏見区鷹匠町8
京都伏見の当社・金札宮は、伏見で最古級の神社のひとつ。
観阿弥の謡曲「金札」や正月の寶惠駕籠、2月の節分祭、5月の神輿渡御などでも知られる。
神木のクロガネモチは京都市指定天然記念物。
15.キンシ正宗 売店前正面

・京都市伏見区紙子屋町554ー1
天明元年中京で創業。
明治13年(1880)さらに名水を求めて伏見に進出。
平成7年(1995)に紙子屋町の本社に工場を集約化するため「新常磐蔵」を建て、横大路の第二みどり蔵跡地は地域活性化を図っている。
16.吟醸酒房 油長

・京都市伏見区東大手町780
伏見の全蔵元18社のお酒を吟醸酒・大吟醸酒を中心に常時80種類以上、季節限定酒などを合わせると100種類以上取り揃えている。
酒蔵を模した店構えが魅力的である。
17.草津みなと残念石

・京都市伏見区横大路草津町
二条城になれなかった残念な石。
寛文2年(1662年)に発生した寛文京都地震で破損した二条城の修築のため、
水路で運ばれた石材が、草津湊で陸揚げされる前に桂川に落下したもの。
2015年に桂川から引き揚げられ、「残念石」として河川敷に置かれている。
18.玄忠寺 伏見義民小林勘次碑

・京都市伏見区下板橋町575
玄忠寺にある伏見義民の碑は、江戸時代初期の元和年間(1615~24)、
淀川を通行する船の料金値上げにより、困窮した伏見町民を、
幕府へのに直訴により救った薪炭商小林勘次を顕彰するものである。
19.戀塚寺(こいづかでら) 袈裟御前戀塚

・伏見区下鳥羽城ノ越町132
袈裟御前の首を供養したと伝える塚(現在は五輪塔)が恋塚。
袈裟御前と恋塚の物語は御伽草子や浄瑠璃に盛り込まれ広がり、鳥羽の恋塚として知られるようになった。
20.久我大臣の墓

・京都市伏見区久我本町4−164
久我は公家の村上源氏の嫡流である久我(源)氏の荘園であった。
源顕房(藤原道長の外孫)の時代は「久我水閣」という別荘が営まれるなど、久我と久我氏のつながりは深い。
明治以降、久我侯爵家により墓地が整備された。
21.御香宮神社表門

・京都市伏見区御香宮門前町
国の重要文化財に指定され、水戸徳川家初代・徳川頼房が伏見城より移築寄進したと伝わる。
三間一戸、切妻造りの単層門である。掲題には名水「御香水」とある。
※人通りが多いのでご注意
22.御大典記念埋立事業竣工碑

・京都市伏見区東柳町(蓬莱橋南詰)
蓬莱橋南詰にある碑は、昭和天皇即位の記念として、水運の役割を終えた宇治川派流の半分を埋め立てた事業の竣工に合わせて建てられた。
当時京都府伏見市であったことから、竣工碑には伏見市長中野種一郎の名前が刻まれ、伏見市の名を見ることができる数少ない史跡である。
23.ササキパン本店

・京都市伏見区納屋町117
大正10年(1921)に「金龍堂」の名で創業。京都で4番目に古いといわれる。
創業当時あんパンは1個5銭で売られ、今も昔ながらの味を大切に受け継いでいる。
レトロな外観にファンが多い。
24.薩摩島津伏見屋敷跡の石碑

・京都市伏見区東境町
薩摩藩邸は濠川沿いで、下板橋の西詰にあった。
薩摩藩の参勤交代での宿所となったほか、13代将軍家定の正室となる篤姫も滞在した。
また、寺田屋での捕縛を逃れ深手を負った坂本龍馬もここに匿われ、療養した。
25.橦木町廓之碑

・京都市伏見区撞木町
撞木町(しゅもくちょう)は、伏見夷町の富田信濃守邸址に開かれた花街である。
街の形状が撞木(鐘を打ち鳴らすT字形の棒)に似ていることからその名が生まれたと伝わる。
一時、山科に暮らした大石内蔵助も度々、撞木町を訪れている。
26.城南宮 神苑 源氏物語 花の庭

・伏見区中島鳥羽離宮町7
「源氏物語」に描かれた80種あまりの草木が植栽されている。
「源氏物語花の庭」として親しまれ、季節ごとに美しさが楽しめる、心安らぐ庭園である。
27.勝念寺 かましきさん

・京都市伏見区石屋町521
釜敷地蔵尊は地獄で釜茹の責めに苦しむ亡者に代わり自ら釜の中で苦を受ける身代地蔵尊である。
「かましきさん」として江戸時代より信仰を集めている。
多羅観音はチベット仏教の流れをくむ仏像としては国内最古に属する。
また、萩の寺しても知られ9月に見ごろを迎える。
28.勝念寺 天明義民柴屋伊兵衛墓所の碑

・京都市伏見区石屋町521
勝念寺にある伏見義民の碑は、天明年間、当時の伏見奉行小堀政方の悪政により伏見の町が衰退するのを憂いて、他の義民と共に幕府への直訴計画に加わった勝念寺の檀家柴屋伊兵衛を顕彰するものである。
政方は罷免されるが、伊兵衛も取り調べ中に病死し、明治以降、伏見のために身命を賭して奔走した人たちを義民として顕彰しようという機運の中で碑が建てられた。
29.新地湯

・京都市伏見区南新地4−31
明治43年(1910)、京阪電鉄の中書島駅が開業し、湿地や水田であった駅の北側は、徐々に開発が進んだ。
昭和になると、駅前と江戸時代からの花街であった中書島を結ぶ道はネオンサインの繁華街となった。
その道沿いにある新地湯の建築は、昭和の時代を彷彿させる。
30.角倉了以水利紀功碑

・京都市伏見区三栖半町487
宇治川派流と旧高瀬川の合流点に建つ。
16世紀後半から17世紀前半の京都の豪商・角倉了以と息子の素庵は、京都伏見間の水運として高瀬川を開通させ、
大坂と京都の中継港としての伏見の発展に寄与した。石碑は了以の偉業を讃えるために建てられた。
31.太閤堤址駒札

・京都市伏見区向島善阿弥町2ー3
秀吉が家康の家臣、松平家忠に堤防普請を命じたとされ、築堤の工事は前田利家が行ったと伝わる。
向島城築城と並行して行われたと伝わる。
32.大黒寺 金運清水

・京都市伏見区鷹匠町4
江戸時代、薩摩藩邸が付近の東堺町に立地し、薩摩藩の祈祷所となる。
18世紀に木曽川治水に尽力し、自刃した薩摩義士の筆頭平田靭負(ゆきえ)、寺田屋事件で亡くなった薩摩九烈士の墓があることや、西郷隆盛と大久保利通が会談した部屋が残ることからも薩摩藩との深いつながりがわかる。
また、境内から涌き出る、「金運清水」は大黒天に供えられる霊験あらたかな水といわれている。
33.竹田火の見やぐら

・京都市伏見区竹田狩賀町
京都市登録有形文化財。竹田村消防組第二支部の装備品として建設。
山型鋼の鉄骨造、総高12mで、地上を含めて6段の台形平面を徐々に逓減させた構成とし、一辺1.2mの正方形平面の望楼部は宝形造の木造鉄板葺屋根を架ける。
現存例が少ない鉄骨造の火の見櫓で、貴重な存在である。
34.田中神社 馬の神様

・京都市伏見区横大路天王後51
横大路と下鳥羽南部の氏神。治暦年間(1065~1069)の創建。
古くは馬借が軒を連ねたことから「馬の神様」として信仰を集めている。10月の神幸祭で神輿が出る。
また境内には、夜泣き、疳の虫封じの北向虫八幡宮もある。
35.谷口清兵衛金物店跡

・京都市伏見区下板橋町
伏見は、豊臣秀吉の桃山城築城の頃から鍛冶の町として知られた所であり、伏見鋸が特に有名であった。
谷口清兵衛金物店は17代続いている老舗で、今は業態を変え、屋号を残している。
正面西側にある地蔵は秀吉の時代からあるといわれ、当時の面影を残す。
向かいにある谷口清三郎商店が、金物店として暖簾を守っている。
36.電気鉄道事業発祥の地碑

・京都市伏見区下油掛町(竹田街道)
明治28年(1895)、京都電気鉄道により、京都駅と伏見京橋(伏見駿河屋横)間に日本初の電気鉄道が開業する。
京橋で大阪との蒸気船に接続し、同年に京都岡崎で開催された第四回内国勧業博覧会への輸送にも貢献した。
大正7年(1918)に京都電気鉄道は京都市電に吸収され、昭和45年(1970)の廃止まで京都・伏見間の旅客輸送に貢献した。
37.鳥羽伏見戦跡碑

・京都市伏見区中島御所ノ内町(鳥羽離宮跡公園内)
慶応 4年(1868)、旧幕府軍と新政府軍は城南宮付近の鳥羽街道(千本通)で戦端を開き、鳥羽・伏見の戦いが始まった。
新政府軍が優位に戦いを進め、旧幕府軍は鳥羽街道を淀方面にに後退する。
開戦時に新政府軍が布陣した秋の山(鳥羽離宮跡公園内)には戦跡碑がある。
38.鳥羽伏見戦の弾痕跡

・京都市伏見区京町3丁目187
老舗料亭「魚三楼(うおさぶろう)」に残る弾痕は、鳥羽・伏見の戦いの際に、伏見奉行所から繰り出す旧幕府軍と大手筋に布陣する新政府軍が京町通でせめぎ合った際に出来たもの。
また、魚三楼の歴史は古く、明和元年(1764 年)創業、薩摩藩の炊事方も務めていた。
39.羽束師坐高御産日神社 久我畷・羽束師川記念碑

・京都市伏見区羽束師志水町219−1
羽束師川造営の偉業を称える記念碑。
低湿地で水はけの悪かった土地に、江戸後期に羽束師川という排水路を構築し、土地改良を行ったことを今に伝える。
40.羽束師坐高御産日神社 本殿

・伏見区羽束師志水町219−1
御祭神は「むずび」の霊力を持つタカミムスビノ神、カンミムスビノ神。
御鎮座は雄略天皇21年(477)と伝わる。
この地は桂川、旧小畑川等河川の合流するところで、農耕、水上交通に恵まれ開けてきました。
羽束師祭(5月)は御創建を祝う伝統ある祭り。
41.東山酒造有限会社 酒蔵外観

・京都市伏見区塩屋町223
もとは左京区新麩屋町で代々酒造業を営み、昭和20年(1945)に法人化。
その後、昭和42年(1967)には伏見区塩屋町に移転した。
昭和47年(1972)に一度伏見区奈良屋町に酒蔵を借りて移転したが、昭和59(1984)年10月にふたたび伏見区塩屋町にもどり、現在に至っている。
※酒蔵の見学は不可
42.平戸樋門

・京都市伏見区豊後橋町
平戸樋門は大正6年(1917)の大水害を契機に宇治川が改修された際に建設。
当初は宇治川上流から宇治川派流への流入を調整していたが、宇治川の河床が下がったため、現在では主に琵琶湖疏水の排水に用いられている。
43.伏見銀座跡

・京都市伏見区銀座町1丁目
慶長6年(1601)、徳川家康によって、銀貨の同一性を確保するために、
日本初の銀座が伏見に設けられ、江戸時代の貨幣政策の礎となった。
その後、駿府、京都、江戸にも銀座が設けられた。
44.伏見駿河屋本店

・京都市伏見区下油掛町174
天明元年(1781)、伏見港京橋の北で諸国大名の乗船待合場所として総本家駿河屋より分家開業した。
以来、二百数十年にわたり「煉羊羹」をはじめ、京菓子の伝統と味、製法技術を守り続けている。
明治28年(1895)に日本初の電気鉄道が走り始めたのは店のすぐ横であった。
45.伏見長州藩邸跡の石碑

・京都市伏見区表町
長州藩邸は江戸時代中期までの古地図や地誌に記載されていないことから、江戸時代後期以降に設けられたと考えられる。
そして、幕末の京都を焼け野原にした禁門の変では、伏見藩邸が拠点となった。
変では長州勢が敗退し、その際の激しい戦闘で藩邸も焼け落ちた。
46.伏見奉行所跡

・京都市伏見区西奉行町(桃陵団地内)
伏見奉行は江戸幕府の遠国奉行の一つ。伏見の民政や淀川水運などを担当した。
伏見奉行には旗本ではなく、5万石級の大名を登用したことからも、その重要性がうかがえる。
伏見奉行所は鳥羽・伏見の戦の際、新撰組などで構成する旧幕府軍の拠点となった。
明治以降、戦前期は陸軍第16工兵大隊が駐屯し、戦後は連合国軍の接収を経て、桃陵団地などになる。
47.伏見桃山城 模擬天守
・京都市伏見区桃山町
昭和 39 年(1964 年)に遊園地(70年にキャッスルランドと命名)を併設して建てられた。
模擬天守の場所は、秀吉、家康が日本を治めた伏見城の北側の曲輪跡である。
当時の伏見城の遺構ではないが、現在は明治天皇陵となった伏見城本丸の天守を考えるきっかけとなる建造物である。
48.伏見夢百衆

・京都市伏見区南浜町247
月桂冠株式会社の本店として、使用されていた大正時代の建造物。
大正8年(1919)に完成した。
現在の喫茶スペースは、新築当時、畳の間だったものを改造したもので、和風建築としての違い棚や欄間、あるいは坪庭などが今も残り当時の様子がうかがえる。
49.松田桃香園

・京都市伏見区新町4丁目
寛永7年(1630)、松田桃香園の初代に当たる茶屋伍兵衛は、宇治茶を生産し、屋号を本家の喜多家よりあやかって“北”の暖簾をあげて、桃香園を開業した。
以来、温故知新の精神で、その時代と共に地元の皆様にご愛顧頂き今日に至る。
店内には、いたるところにお茶の歴史を感じる看板や茶壷、表彰状が飾られている。
50.三栖閘門

・京都市伏見区葭島金井戸町
大正6年(1917)の大洪水をきっかけにした淀川の治水工事により、舟運に影響が出ないように建設された施設。
閘門内でエレベーターのように水位を調整し、水位の異なる宇治川派流(伏見の港)と宇治川(淀川)の間での舟運を可能にした。
伏見港の基幹となる存在。
51.水ノ雅 KYOTO FUSHIMI

・京都市伏見区京町1丁目244
齊藤酒造社長元私邸を引き継いだレストラン。
築150年の歴史の重みと和の温かみも感じられる。
伏見の契約農家から届く野菜は旬の恵みがつまっており、シェフが素材の良さを引き出して創る京フレンチは、繊細で優雅である。
52.明壽院 伏見庚申堂 くくり猿

・京都市伏見区桝屋町614
庚申尊の眷属である三猿をお祀りしている。
見ざる、言わざる、聞かざるで広く知られている。くくり猿は、庚申尊の眷属である猿を現したもの。
古来、魔除けとして軒先に吊られている。伏見庚申堂のくくり猿は、胎内に庚申尊の護符が入っている。
53.向島中央公園

・伏見区向島二ノ丸町151
向島ニュータウン内で向島駅から国道24号沿いの商業施設まで帯状に600m続く向島中央公園。
地下水をくみ上げたせせらぎと70種以上の植物が茂り、憩いの場になるとともに、地域交流の場となっている。
54.澱川橋梁

・京都市伏見区向島西堤町31−6
1928 年に近鉄京都線の前身奈良電によって架けられたトラス橋。
当時、宇治川での陸軍の架橋演習に支障がないよう無橋脚橋梁として建設され、全国の単純トラス橋で最大級の大きさを誇る。
登録有形文化財(建造物)に指定される。
55.淀城跡

・京都市伏見区淀本町 168
淀城跡公園淀城は、廃城となった伏見城の資材などを活用し、桂川、旧宇治川、旧木津川が合流する川中島に築城された。本丸石垣の一部が往時の名残をとどめる貴重な史跡である。
寛永3年(1626)の二条城行幸の際には、徳川家光が2カ月に渡って上方での居館とし、公家や武家が多数謁見に訪れた。
56.與杼神社 銀杏と拝殿

・京都市伏見区淀本町167
與杼(よど)神社は、淀・納所・水垂・大下津の産土(うぶすな)神として鎮座している。
祭神は、中央に豊玉姫命(トヨタマヒメノミコト)
向かって右側に高皇産霊神(タカミムスビノカミ)
向かって左側に速秋津姫命(ハヤアキツヒメノミコト)の三柱。
対に並ぶ銀杏の木が美しい。
57.淀水路の河津桜

・京都市伏見区淀新町
河津桜は2月から見頃を迎える桜として、全国的に人気が高まる中、関西で随一の名所が「淀水路の河津桜」である。
2月から美しい花を楽しむことができるスポットとして、関西一円から観光客が集まる。
300本という大規模な桜並木が見られるのは、関西ではここだけとされる。
58.淀の水車モニュメント

淀の水車は、淀川から城内に水を引くために設けられ、かつての淀城の象徴であった。
伏見と大坂を結ぶ水運で淀川が賑わった江戸時代は、淀のランドマークであった。
平成28年(2016)に、淀駅前にモニュメントが造られ、現在は待合せスポットにもなっている。
59.「龍馬とお龍、愛の旅路」像

・京都市伏見区西柳町
慶応2年(1866)寺田屋宿泊中の坂本龍馬は伏見奉行所配下の捕り手に囲まれる。
この異変を寺田屋のお龍からいち早く、知らされていた龍馬は、深手を追ったものの伏見薩摩藩邸へ逃れることができた。傷が癒えた龍馬はお龍とともに、静養先の九州に向けて、伏見の浜から旅立った。
60.竜馬通り商店街 竜馬アート

・伏見区車町
商店街の至る所に描かれた竜馬アート。
竜馬通り商店街は京町家風の外観とレトロな雰囲気で観光客に愛され続ける商店街。
店舗シャッターに描かれた竜馬のイラストは「伏見+アートフェスティバル」という企画で行われたもの。
61.長建寺 竜宮門

・京都市伏見区東柳町511
元禄11年(1698)、伏見奉行に任じられた播磨林田藩主建部内匠頭政宇は、
在任中に湿地であった中書島を開発し、北に蓬莱橋、西に今富橋を架橋した。
そして、東に建立された長建寺は、本尊を八臂弁財天とし、今も多くの人の信仰を集めている。
62.安楽寿院 地図付き解説板
・京都市伏見区竹田中内畑町74
安楽寿院と付近一帯は平安時代後期(11~12世紀)、鳥羽離宮が営まれ院政による政治の中心地であった。
離宮の規模は東西約1.2~1.5 km、南北約1kmに及ぶ。
鳥羽離宮はその後の災禍で失われ、わずかに安楽寿院にその系譜が受け継がれている。
63.月の桂 株式会社増田德兵衞商店
・京都市伏見区下鳥羽長田町135
延宝3年(1675)創業の酒蔵。
江戸時代後期には京から西国へ向かう公家の中宿を務め、明治以降も著名人が多く訪れた。
滑稽新聞の発行者として知られる宮武外骨や早大名誉教授で美術史研究で名を馳せた会津八一が好んで逗留し、当主と親交を深めた蔵元としても知られる。
64.八千代大明神(平戸町)
・京都市伏見区平戸町737−1
別名、剣先稲荷。
天保9年(1838)に伏見奉行となった信濃岩村田藩主内藤豊後守正縄は、伏見に善政を敷き、御香宮には正縄の武運長久を祈る灯籠もある。
正縄は庶民のために平戸町を桜の名所として開発、その中心に剣先稲荷が据えられた。
一帯は鳥羽伏見の戦いで焼失するが、社は後に再建。
65.淀本町商店街
・京都府京都市伏見区淀本町
お花見スポット「淀水路の河津桜」の開花に合わせ、
2025年3月1日
(土曜日)、2日(日曜日)の2日間「淀本町商店街桜まつり2025」が開催。
淀本町商店街には、老舗の和菓子店、豆腐店、揚物店など昔ながらのお店から、
お洒落なカフェ、ナッツバタードリンク店など今どきのグルメなお店までバリ
エーション豊かなお店が集まる。
※区民・史跡めぐりの景品の当選対象となる投稿日は、3月2日(日曜日)のみです。
その他・イベント
66.伏見区民文化祭
・京都市伏見区鷹匠町 伏見区役所4階大会議室、1階ホールなど
3月2日(日曜日)午前10時~午後2時
区民の皆様による日頃の文化活動を発表していただく晴れ舞台として、開催します。
問合せ先
伏見区役所地域力推進室まちづくり推進担当
〒612-8511 京都市伏見区鷹匠町39番地の2
TEL:075-611-1144 FAX:075-611-0634
お問い合わせ先
京都市 伏見区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:企画担当:075-611-1295、事業担当・広聴担当・振興担当:075-611-1144
ファックス:075-611-0634