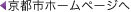語りつがれるわがまち
ページ番号38847
2012年9月25日
このページは,中京しんぶん平成19年4月15日号から平成21年3月15日号にかけて連載した,各学区の現況や取り組みを紹介している記事です。
語りつがれるわがまち
中京区は昭和4年4月に上京・下京より分区し,文字どおり京都市の中心として誕生しました。以来,先人から引き継がれた町衆の心意気と高い自治の意識に支えられ,政治・経済・文化の機能が集積した素晴らしいまちに発展してきました。
しかしながら今日,マンションやビルの増加により町並みが変容するとともに,高齢化や核家族化が進み,地域社会のあり方が問われています。
このような時代にこそ,思いやりの「心」,人と人との「和」が今までにも増して必要とされています。
日本の小学校の先駆け 番組小学校
京都では,明治に入ると町組改正が行われました。同時に町組ごとに小学校を建設するという構想が立てられ,国の学制発布(明治5年)に先立ち64の番組小学校が誕生しました。その際,小学校の建設費用の多くは地元有志の寄付金などで賄われました。京の町衆の教育にかける熱意をうかがい知る事ができます。
ところで,中京区の元学区は,日本の小学校の先駆けとなった15の番組小学校と朱雀8学区の23学区で構成されています。

元学区概図
中京区の変遷
● 明治元年,自治組織としての番組が成立
● 明治2年,町組が改正され,三条通を境に,北が上京,南が下京となる。
● 明治12年,上京・下京の両区域に「区」の名称が付される。
● 明治22年,京都に市制が施行される。壬生,西京,聚楽廻の各村統合により葛野郡朱雀野村となる。
● 大正7年,大規模な市域拡大が目指され隣接市町村の京都市編入が相次ぎ,朱雀野村を下京に編入する。
● 昭和4年,上京区・下京区から分区して中京区が誕生する。
● 昭和16年,朱雀学区が8学区に分かれる。
各学区の紹介
平成19年5月15日号 梅屋学区 平成19年6月15日号 朱雀第一学区
平成19年7月15日号 竹間学区 平成19年8月15日号 朱雀第二学区
平成19年9月15日号 富有学区 平成19年10月15日号 朱雀第三学区
平成19年11月15日号 教業学区 平成19年12月15日号 朱雀第四学区
平成20年1月15日号 城巽学区 平成20年2月15日号 朱雀第五学区
平成20年3月15日号 龍池学区 平成20年4月15日号 朱雀第六学区
平成20年5月15日号 初音学区 平成20年6月15日号 朱雀第七学区
平成20年7月15日号 柳池学区 平成20年8月15日号 朱雀第八学区
平成20年9月15日号 銅駝学区 平成20年10月15日号 乾学区
平成20年11月15日号 本能学区 平成20年12月15日号 明倫学区
関連コンテンツ
語りつがれるわがまち
- 語りつがれるわがまち「梅屋学区」
- 語りつがれるわがまち「朱雀第一学区」
- 語りつがれるわがまち「竹間学区」
- 語りつがれるわがまち「朱雀第二学区」
- 語りつがれるわがまち「富有学区」
- 語りつがれるわがまち「朱雀第三学区」
- 語りつがれるわがまち「教業学区」
- 語りつがれるわがまち「朱雀第四学区」
- 語りつがれるわがまち「城巽学区」
- 語りつがれるわがまち「朱雀第五学区」
- 語りつがれるわがまち「龍池学区」
- 語りつがれるわがまち「朱雀第六学区」
- 語りつがれるわがまち「初音学区」
- 語りつがれるわがまち「朱雀第七学区」
- 語りつがれるわがまち「柳池学区」
- 語りつがれるわがまち「朱雀第八学区」
- 語りつがれるわがまち「銅駝学区」
- 語りつがれるわがまち「乾学区」
- 語りつがれるわがまち「本能学区」
- 語りつがれるわがまち「明倫学区」
- 語りつがれるわがまち「日彰学区」
- 語りつがれるわがまち「生祥学区」
- 語りつがれるわがまち「立誠学区」
お問い合わせ先
京都市 中京区役所地域力推進室総務・防災担当
電話:庶務担当075-812-2420 地域防災担当、調査担当、企画担当075-812-2421
ファックス:075-812-0408